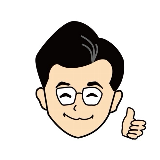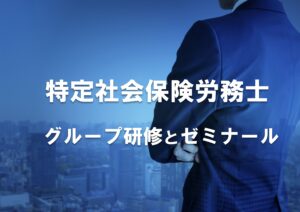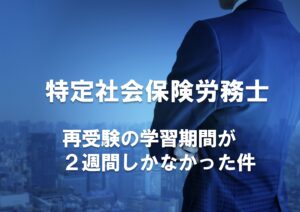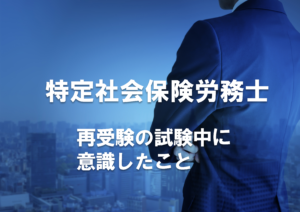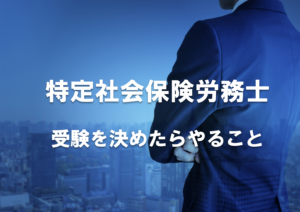「特定社労士、気になってはいるけど情報が少ない…」
そう感じている方、いらっしゃいませんか?
 うっちー
うっちー私もそうでした。
前々から興味はあったものの、申し込み方法も学習のすすめ方もいまいちよく分からなかったのです。
2021年度に実際に経験してみると、「より早い段階でこうしておけばもっと楽だったのに!!」ということがぽろぽろ出てきました。
ですので、私自身が感じた「こんな情報があればよかった」ということをブログに書き残しておきます。
今回は、特別研修の参考図書についてです。



試験対策本についてはこちらの記事でご紹介しています!


研修に必須の本
最新重要判例200
近年の傾向では2年ごとに冬から春にかけて改訂版が出ているようです。
| 改訂版出版履歴 | |
|---|---|
| 2024/2/21 | 第8版 |
| 2022/12/2 | 第7版 |
| 2020/3/27 | 第6版 |
| 2018/3/2 | 第5版 |
特別研修では、この判例集を持ってきているていで話が進みます。
研修課題を検討するにあたって「参考となる判例は?」「それに関連する判例は?」など、バンバン当てられて聞かれました。
特別研修のテキストが手に入ったら、課題に関連する判例を事前に調べておいたほうがいいですよ。
ポケット六法
これも、持っているていで研修が進みます。
近年の傾向では毎年9月に改訂版が出ています。
| 改訂版出版履歴 | |
|---|---|
| 2024/9/20 | 令和7年版 |
| 2023/9/22 | 令和6年版 |
| 2022/9/21 | 令和5年版 |
| 2021/9/17 | 令和4年版 |
タイトルに「ポケット」と付きますが、実物は辞書のような厚みのある本です…ほんまもんの六法に比べたらはるかに小さいのですけど。



何かと荷物が多くなる特別研修で、この重さはなんぎ…
そう感じる場合は、代替品もあります↓
労働関係法規集
ポケット六法の代わりとして使える本です。
近年の傾向では毎年3月に改訂版が出ています。
| 改訂版出版履歴 | |
|---|---|
| 2025/3/14 | 2025年版 |
| 2024/3/19 | 2024年版 |
| 2023/3/29 | 2023年版 |
| 2022/3/29 | 2022年版 |
| 2021/3/1 | 2021年版 |
先に特別研修を受けた先輩に教えていただき、私はこちらにしました。



サイズがコンパクトです!
参加者の大半はポケット六法を使っているので、研修の際に講師の先生から「六法の〇〇ページを開けてください」と言われたときに違うページを探すことになります。それでも特に支障はありませんでした。
労働関係法規集は出版数が少ないようで品薄です。
こちらで代用したい方は、販売しているのを見つけたら即ゲットしたほうが良いと思われます!



判例集とポケ六(or法規集)の2つは研修に必須ですのでご準備をお忘れなく!!
その他の参考図書
労働法(菅野和夫先生)
言わずと知れた『労働法』
改訂の傾向が掴みにくいですね…
| 改訂版出版履歴 | |
|---|---|
| 2024/4/11 | 第十三版 |
| 2019/11/28 | 第十二版 |
| 2017/2/13 | 第十一版補正版 |
| 2016/2/25 | 第十一版 |
こちらは特別研修の参考図書の一覧にもあげられています。
かなり骨太な本ですので、研修に持参するというよりも実務家として事務所に備え付けておく本といった感じです。
労務トラブル予防・解決に活かす 菅野労働法
上記の『労働法』をもとに、事例を交えてわかりやすく解説してくださっている本です。
一つのテーマごとに次のような構成になっています。
事例 ⇒ 問題の所在 ⇒ 実務上の留意点 ⇒『労働法』からの引用 ⇒ 『判例』
事例から入ってくれるので、争点がイメージしやすく、読み物として読み進めてくことができます。



ストーリー性のあるもののほうが、頭に入りやすいですよね。
こちらも、前年度に合格された先輩から教えていただいたものです。
研修にも試験対策にも役立ちますし、また、特定を受験するかどうかに関わらず勉強になる本です。私は買ってよかったです。
労働紛争あっせん代理実務マニュアル
特定はそもそも『あっせん』について学ぶので、その実務について書かれている本は参考になります。
じつは、特別研修では『あっせん申請書』や『答弁書』ついて、書き方のレクチャーが特に無いまま、見よう見まねで課題を作成しなくてはなりません…
いちおう研修資料に見本があるのですが、サラッとだけです。
そこで、この本を特別研修のグループ研修に向けて読んでおくとためになります。



私はグループ研修の後でこの本を知りましたが…
労働事件審理ノート第3版
これは、ゼミナールで講師をされていた弁護士の先生からご紹介いただいた本です。
ブロック図で要件事実を整理して示しています。
事件に法的根拠を当てはめていく手順の勉強になります。
申請書・答弁書のモデルも掲載されていますので、特別研修の課題作成の参考にもよいです。
最新版の発行が2011年と古いのですが、法令というよりも考え方を学ぶ本なので、古くても役に立ちます。



パッと見は、少しとっつきづらい雰囲気です…
まとめ
特別研修と紛代試験の費用と交通費・宿泊費だけでもなかなかの出費になるのですが、それに加えて研修に持参する本や試験対策本の費用も必要です。
ここに掲載した本を参考にしていただき予算を見込んでおけば、後で想定外の出費に焦らずに済むでしょう。
また、他の記事でも申し上げていますが
特に、合否を決定するといっても過言ではない『倫理』は、早めに試験対策を始めておいた方がいいです。
試験対策本はこちらでご紹介しています